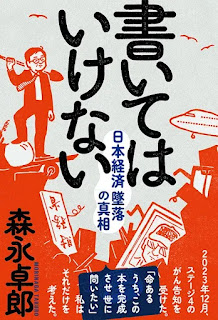個人的に今年は邦画の当たり年。以下の4本は特に良し。
●最優秀作品賞
『正体』(監督:藤井道人/製作2024年、日本)
まあ、この監督とキャスティングで外れることはないだろうな…と思っていたが、期待通りの大当たり。「逃亡犯・鏑木慶一」役の横浜流星の確かな成長、その表現力に心打たれつつ、緊迫感みなぎる逃亡劇に見入った。(「鏑木」を追う刑事・又貫を演じた山田孝之の“らしからぬ重厚感”も印象的。で、新発見。吉岡里帆って、こんなにイイ役者だった?)
●優秀作品賞
『青春18×2 君へと続く道』(監督・脚本:藤井道人、原作:ジミー・ライ/製作2024年、日本・台湾合作)
これも藤井道人監督作品(脚本まで手掛けている)。しかも“青春映画の宝庫”台湾も舞台になっていると聞けば「観たい」と思うのは(私的に)必然。18年前の台湾と現在の日本を舞台に、国境と時を超えて紡がれるLoveストーリー、その意想外の展開に「なるほど、そういう事だったのか…」と、驚きつつ、少し濡れてしまった目を凝らしながらの123分だった。
(で、そのエモーショナルなストーリーもさることながら、この作品の最大の魅力は稀有な“初恋の記憶”を観客の胸に強く残した二人の存在、清原果耶と台湾の人気俳優シュー・グァンハン。とりわけ、初恋に心躍らせる18歳の素朴な台湾男子と、人生の岐路をそれなりに乗り越え大人の魅力を漂わせる36歳のジミーを見事に演じ分けたシュー・グァンハンの演技と佇まいは、台湾スターらしい確かな輝きを放つものだった。)
『ラストマイル』(監督:塚原あゆ子/製作2024年、日本)
この「ラストマイル」に関しては観る前から、評判の高さも含めてかなりの情報が頭に入っていて、期待値上がり過ぎ…の感あり。それ故、鑑賞後の満足度は中の上or上の下、と言ったところだが、もちろん面白かったし、「観て損はなかった」と思える一本。労働条件が悪化し続けるエッセンシャルワーカーの過酷な現実を描き出した面でも、評価されて当然の作品だと思う。満島ひかり、岡田将生の好演は言わずもがな。個人的には、11月に亡くなった「俳優・火野正平」の姿をスクリーンで拝めたことが嬉しかった。(「こころ旅」の一ファンとして、改めて合掌)
『侍タイムスリッパ-』(監督:安田淳一/製作2024年、日本)
今年8月、私もちょくちょく利用するレトロな映画館「池袋シネマ・ロサ」一館のみで封切られ、口コミであっという間に広がり、いまや全国100館以上で順次拡大公開されている超話題作。(監督・脚本・カメラ・キャスティング・宣伝ポスター等々、すべてを一人の人間が行い、信じられないほどの低予算で製作されたことでも話題を呼んだ)
何故それほど多くの人たちに支持されたのか? まあ、それは映画を観れば分かることだが、一言で言えば「本当に面白くて、楽しめて、人の心に添える優しい映画だから」ではないだろうか。ドラマ「JIN-仁」の桂小五郎役、「剣客商売」の秋山大治郎役が記憶に残る主演・山口馬木也の演技と殺陣も見事だった。
さて、残すところ、今年もあと1日。
来るべき2025年が皆様にとって良い一年でありますように。